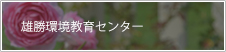石巻市雄勝町は、石巻市大川地区から車で5分の場所に位置し、町の中心部は雄勝湾に面した商店街でした。3・11の大津波によって浸水高19mの津波に襲われ、中心部のほぼ100%が壊滅しました。亡くなった方は町全体で243名(内不明者70名)にのぼりました。震災後に立ち上げた非営利型の一般社団法人「雄勝花物語」では、東日本大震災の体験を基にした「津波防災教育プログラム」と「震災復興の学びのプログラム」を実施しています。
本団体の「防災教育1」の担当者は、津波から子どもたちを避難させた体験をもつ元宮城県公立学校教員,「防災教育2」の担当者は、HORITON波力研究所の堀込智之先生(工学博士)です。また、被災地教育旅行を対象とした「ボランティア活動」や新人社員研修などを目的とした「企業研修」も受け入れています。 【受け入れ場所:雄勝ローズファクトリーガーデン】住所:石巻市雄勝町字味噌作34-2 【時間:午前9時~午後4時まで】
![]()
津波防災教育プログラム の内容
【防災教育1】は、2011年3月11日の巨大津波に襲われた石巻市立雄勝小学校の避難行動と大川小学校の避難行動の検証を通して立案した、「津波防災教育プログラム」です。
宮城県全体では小学生から高校生353名が亡くなりましたが、学校管理下の大川小学校の74名を除いて、279名が自宅や地域で亡くなっています。この意味することは、学校の避難訓練(お・は・し)では、地域に帰った子どもの命を救えなかったということです。この反省の下に子ども一人一人が地域に帰ってからも自分の命を自分で守ることができる防災能力(先生がいなくても、大人がいなくても自分で守る防災能力)を育てる必要性を痛感して立案しました。た本プログラムは、具体的・実践的な「津波防災教育プログラム」です。
進め方は、映像やアニメーション等を活用した講義を聴いて、受講者が自ら考えたりディスカッションしたりする授業形式で行います。講義の後は当団体の裏山に登って、津波高28m(浸水深20m)の津波到達地点から地上を見ろしていただきます。陸地の奥に行くほど狭くなるという地形によって津波がせり上がってくるというリアス海岸を襲う津波の特徴をイメージすることができます。雄勝湾を襲った津波の巨大さと恐ろしさを体感することができる体験プログラムです。
対象者:学校の教職員、小中高校生、大学生・院生、社会人
- 担当 : 本団体共同代表 徳水博志(元宮城県公立学校教員/元宮城教育大学非常勤講師/元東北工業大学非常勤講師/現在、石巻市教育委員会社会教育委員)
-
《防災教育1の内容》
-
1、自分の地域を襲う津波について正しく知る
- ①津波は大津波警報の高さ(平均的な値)ではやって来ない! *実際の津波の高さは1/2~2倍の幅がある。つまり大津波警報10mの意味とは「平均的な値」であり、津波高5m~20mの津波を意味する。
- ②津波は海岸地形や陸上地形で高くなり、都市部ではビル等の構造物で高くなる。
- ③自分の地域の地形や構造物を理解して、地域を襲う津波の高さや特徴をイメージして避難行動とる必要性。
- ④ハザードマップを過信しない(自然界では人間が設定した条件を超える予見不能な現象が発生)
-
2、自分の地域の災害リスクを知る
- ・実際に自分の住んでいる地域の「災害リスク」を調べてみましょう。
- ・皆さんはどんな地域に住んでいるのでしょうか?
- *受講者が暮らしているまちの地形と地盤を調べて、地震・津波・洪水・土砂災害の歴史を提示します。 自分の地域の「災害リスク」を知ることで、他人事から自分事への意識の転換を図ります。
-
3、より安全な避難マニュアルを考えて、実行する
- ①いつ・どこへ・どんな方法で、 ②幾通りも!
4、判断力と行動力を鍛える
・避難マニュアル通りにはいかない。想定外は必ず起きる! 「クロスロードゲーム」で判断力を鍛えましょう。
-
【雄勝小学校の避難行動の検証と防災上で学ぶべき教訓】
- 雄勝小学校の教職員の一人であった私は、3.11当時、避難マニュアル通りの避難行動ができませんでした。その理由は、大津波警報10mの津波が雄勝湾のリアスの地形によって、1.6倍の高さに増幅するという巨大津波のイメージを十分に持っていなかったからです。そのために山への避難を訴えた住民の叫び声を聞くまで校庭に留まり続けて、裏山への避難が遅れてしまったのでした。もし大津波警報10mは「平均的な値」と知っており、雄勝湾のリアスの地形では津波が1.6倍に増幅するという特徴を事前に知っていたならば、地域を襲う津波の大きさをイメージすることができて、もっと早く安全に裏山に避難していたであろうと思います。学ぶべき教訓は、リアスの地形では陸地の奥に行くほど津波が高くなるという特徴がありますから、遠くに逃げても助かりません。近くの裏山に「垂直避難」することが避難方法の鉄則です。
-
【大川小学校の避難行動の検証と防災上で学ぶべき内容】
- 大川小裁判における仙台高裁判決では、「事前防災に関し、校長ら大川小幹部と市教委に組織的過失があった」と認定されました。つまり大川小学校事故の最大の要因は事前防災(避難マニュアル等の不備)の欠如でありました。避難マニュアルに一言「裏山に避難」と書いてあれば助かった命でした。ただしこの裁判でもなぜ三角地帯(堤防道路)に向かったかのかは解明されませんでした。この疑問に答えてみたいと思いました。あくまでも一つの推論にすぎませんが、大川小学校の先生方は大津波警報10mの津波が校舎までやってくるというイメージ(危険予測)をもっていなかったと思われます。1つ目に北上大橋の堤防を越えて津波が来るというイメージを持っておれば、決して三角地帯(堤防道路)には向かわないはずです。2つ目に奥に行くほど狭くなるという大川(釜谷)地区の地形によって海岸から陸上伝いにやって来た津波が高くなるというイメージ(危険予測)を持っておれば、津波が校舎まで押し寄せて来ることを予測し、倒木等のリスクがあったとしても裏山に避難していたはずだと考えられます。防災上の学ぶべき内容とは何か。自分の地域を襲う津波の高さや特徴をイメージ(危険予測)して、避難行動を起こす(危険回避)大切さです。これも学ぶべき内容の一つではないかと思います。受講者の皆さんと共に考えていきます。
- 【学校の教職員が身に付けたい津波防災能力】の提案
- 仙台高等裁判所は、教育行政及び管理職と一般教員に対して、「事前防災の重要性」と「地域住民の平均的な知識・経験よりも高いレベルの防災知識の必要」を提言しました。それについて下記の案を提案しています。
津波防災能力(危険予測・回避能力)とは
(1)津波についての新しい知見(正しく知る)
①大津波警報10ⅿの意味(平均的な値)の知識
②地形で変化する津波の特徴の知識
③津波ハザードマップの解釈の仕方
④地震と津波との関係の知識(特に震源地までの距離と津波との関係の知識等)
⑤地域の地形、津波災害の歴史等の地域の災害リスクについての知識
(2)情報収集能力
・津波に関する情報をテレビ・ラジオ・スマホ・地域の人から収集する能力
・津波に関する情報を自分の足と目で収集する能力
・現在の地域の情報(道路などの交通状況、地震の被害状況等)を収集する能力
(3)地域を襲う津波の大きさのイメージおよび災害をイメージする想像力
・想定津波〇〇メートルから地域を襲う津波をイメージする想像力
・津波で引き起こされる災害をイメージする想像力
(4)想定外に対処できる主体的で迅速な判断力と行動力
・避難マニュアルに縛られることなく、想定外に臨機応変に対応できる主体的で迅 速な判断力と行動力
震災語り部 の内容
- 1.雄勝小学校の避難経路の現地案内と避難方法から学ぶ教訓
- 2.雄勝小学校に避難を呼びかけた住民(保護者)の方の語り部と教訓(中止)
![]() 語り部活動
語り部活動
概要
- 【防災教育】*高校生以下の料金は半額程度に軽減します。
- ・語り部ガイド現地案内60分1団体1万円(人数5人~50人程度)
- ・防災教育1(担当者:元宮城県公立学校教員)60分
- *語り部ガイド現地案内と防災教育1をセットで学ぶ場合は上記の合計金額です。
- 料金:1~10人まで一律15,000円、11人以上お一人1,500円
- 人数:40人程度、大人数の場合は別会場(雄勝体育館や雄勝公民館:会場費有料)
- 【震災復興の学び】
- ・被災児の心のケア60分
- ・地域復興を学ぶ総合学習60分
- ・SDGS震災後のまちづくり(雄勝花物語の歩みと雄勝ガーデンパーク事業) 60分
- 料金:1~10人まで一律15,000円、11人以上お一人1,500円
- 人数:40名程度、大人数の場合は別会場(雄勝体育館や雄勝公民館:会場費有料)
お問い合わせ・予約
携帯 090-3365-4114 防災教育担当 徳水博志
震災復興の学びのプログラム
(1)復興プロジェクト「雄勝花物語」の学び
・復興プロジェクト「雄勝花物語」の歩みや雄勝町の復興に果たす役割などについて学ぶプログラムを提供します。
・対象者 :企業研修者、大学生・大学院生、被災地教育旅行生(小学生・中学生・高校生)
(2)復興教育「被災児の心のケア」のプログラム
・東日本震災を体験した雄勝小学校の子どもたちの心のケアを行った教育実践を学ぶプログラムです。「心理社会的ケアプログラム」の手法を使って、震災体験と向き合い、辛さを語り、記録することで震災を乗り越えようとした震災2年目の歩みです。ドキュメンタリー映画DVD「ぼくたちわたしたちが考える復興~夢を乗せて~」および「第29回東書教育賞最優秀論文《震災体験の対象化を通して被災児の心のケアの試み》」を教材に使って学ぶプログラムです。第29回東書教育賞最優秀論文>
・対象者:教員志望大学生・大学院生、被災地教育旅行生(小学生・中学生・高校生) *有料プログラム60分
(3)復興教育「地域復興を学ぶ総合学習」のプログラム
・雄勝小学校の「復興教育」は当時教諭であった徳水博志氏が、2012年6月に提案した全国で最初の「復興教育」です。その提案書は『東日本大震災と教育界』(明石書店2013年)に収録されていますが、「震災復興を担う教育観への転換」として、1.子ども観の転換 2.学力観の転換 3.学校経営観の三つの転換を提唱しました。詳しくは『東日本大震災教職員が語る子ども・いのち・未来』(明石書店2012年)をご覧下さい。本プログラムは、雄勝小学校の「復興教育」の2年間の総合学習を学ぶプログラムです。教材は下記の2つの実践記録です。
・2011年度6年生の教育実践「震災復興まちづくりプラン」、YouTube動画ダウンロード
・2012年度5年生の教育実践「雄勝湾のホタテ養殖と漁業の復興」 日本児童教育振興財団制作 DVD「ぼくたち私たちが考える復興・夢を乗せて」
・対象者 :教員志望大学生・大学院生、被災地教育旅行生(小学生・中学生・高校生) *有料プログラム60分
・参考文献1 「生存の東北史」大月書店2013年 生存の東北史 第7章「生存の足場を創る現在の試み~小学6年復興まちプラン~」
生存の東北史 第7章「生存の足場を創る現在の試み~小学6年復興まちプラン~」
・参考文献2 「東日本大震災 教職員が語る子ども・いのち・未来」明石書店2012年
・参考文献 3  PDF 第29回東書教育賞最優秀論文 徳水博志著「震災体験の対象化」による被災児への《心のケア》の試み
PDF 第29回東書教育賞最優秀論文 徳水博志著「震災体験の対象化」による被災児への《心のケア》の試み
(4)ESD (雄勝町の震災復興の現状と課題)のプログラム
・石巻市雄勝町の復興の現状と課題について学ぶプログラムです。「雄勝地区震災復興まちづくり協議会」の委員を務めた本団体の担当者が雄勝町の復興の現状と課題を報告します。「高台移転・職住分離・多重防御」という国と県の方針は、雄勝町中心部の人口流出を招き、町の衰退に拍車をかけました。L1津波に対応した9.7mの防潮堤の建設、環境アセスメントなしの災害復旧事業は森と海がつながった雄勝湾の生態系を壊し、美しい海岸景観を壊します。持続可能な町を作るためには何が必要か、地域資源の海の食材と雄勝石を生かした雄勝のまちづくりの可能性と現状を学び、過疎地の再生と持続可能な地域を創る方策(6 次産業化、グリーンツーリズム、地域内経済循環、復興の主体形成、後継者育成)を共に考えるプログラムです。
・対象者 : 企業研修者、 大学院生・大学生 *有料プログラム60分
防災教育&復興教育資料の展示
・雄勝町の震災直後の様子や「雄勝花物語」の復興活動の写真展示、語り部の資料などを展示しています。
・「心理社会的ケアプログラム」(東北クリニック心療内科医桑山紀彦医師の提唱)によるジオラマ作品(2012年度雄勝小学校5年生)と2011年度雄勝小学校6年生が考えた雄勝町の震災復興プラン(立体模型)を展示しています。
・雄勝小学校の《復興教育》から生まれた5年生児童の版画共同作品「希望の船」を展示しています。
・2012年度5年生の《復興教育》の実践記録:DVD『ぼくたちわたしたちが考える復興・夢をのせて』(日本児童教育振興財団発行)を無料でご覧いただけます。上映時間は参加者の随時で60分です。
![]()
![]()
震災学習の記録 DVDの上映
日本児童教育振興財団制作のDVD『ぼくたちわたしたちが考える復興・夢をのせて』は、雄勝ローズファクトリーガーデンで随時ご覧になれます。また日本児童教育振興財団で貸出を行っています。 日本児童教育振興財団 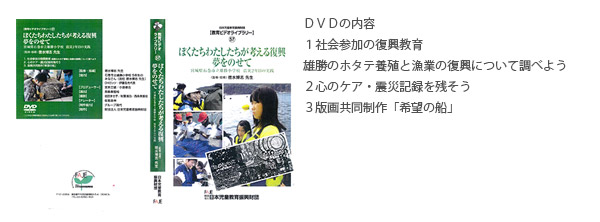
被災児の心のケアの論文(ダウンロード可)
 ・PDF 徳水博志著「震災体験の対象化」による被災児への《心のケア》の試み 第29回東書教育賞「最優秀賞」受賞論文 ダウンロード先
・PDF 徳水博志著「震災体験の対象化」による被災児への《心のケア》の試み 第29回東書教育賞「最優秀賞」受賞論文 ダウンロード先
 ・PDF 雄勝オーリンクハウス・徳水博志共催「ふるさと復興子ども版画展」
・PDF 雄勝オーリンクハウス・徳水博志共催「ふるさと復興子ども版画展」


ボランティア活動受入
震災から3年後に被災地のがれき撤去は終了しましたが、被災地でボランティア活動を行いたい、被災者と交流したいというご要望は絶えません。そのご要望にお応えするために、雄勝ローズファクトリーガーデンでは、花の植栽、除草、造成などのボランティア活動を受け入れています。2013年から中学・高校・大学生の教育旅行および企業研修を受け入れています。ガーデン造成にご協力いただいたボランティア団体は2015年4月現在で80団体以上、3000人以上に上ります。 ボランティア活動の時間は、柔軟に設定できます。また震災語り部、防災教育を組み合わせたプログラムも用意しています。
ボランティアの活動プログラム *時間設定は下記例示以外にもご相談に応じます
- ・1コマ90分です。午前、午後どちらでも設定可です。
- ・活動内容は除草・植栽・施肥・造成(季節によって変わります)
- ボランティア活動と語り部・防災教育を組み合わせたプログラム例
- ②ボランティア活動1コマ+語り部のプログラム 合計150分
- ・ボラ 90分(午前、午後どちらでも設定可)
- ・語り部(現地案内含)60分
- ③ボランティア活動1コマ+語り部+防災教育(半日コース)
- ・ボラ 90分(午前、午後どちらでも設定可)
- ・語り部(現地案内含)60分
- ・防災教育 60分
- ④ボランティア活動2コマ+語り部+防災教育(1日コース)
- ・ボラ 90分×2コマ=180分
- ・語り部(現地案内含)60分
- ・防災教育60分